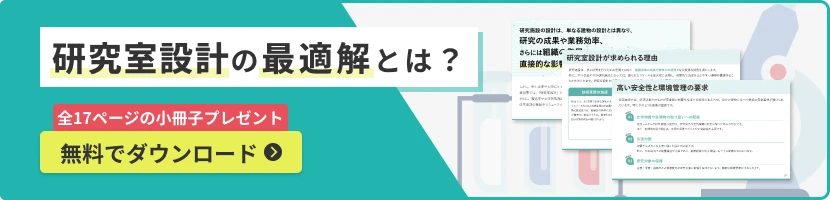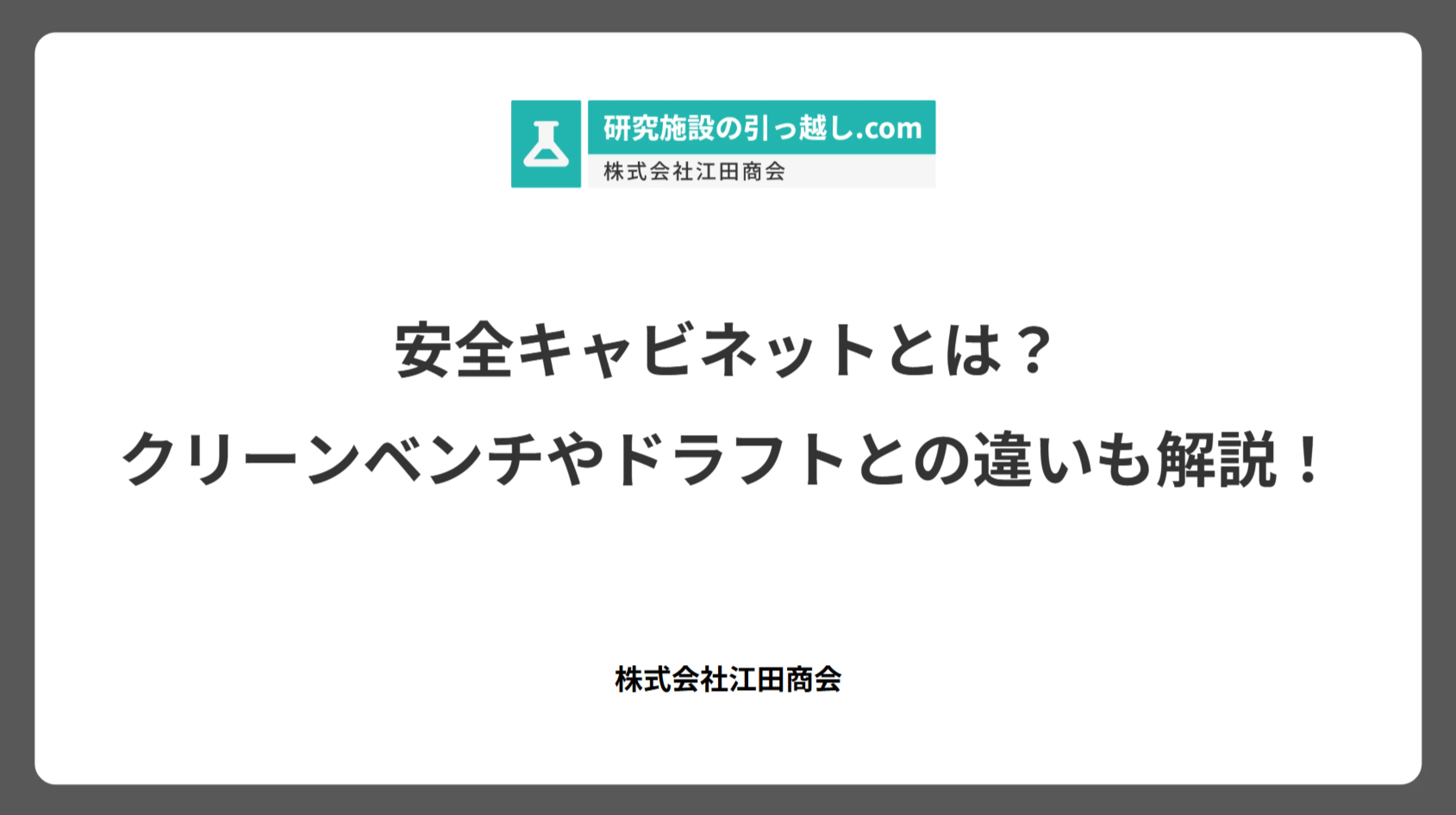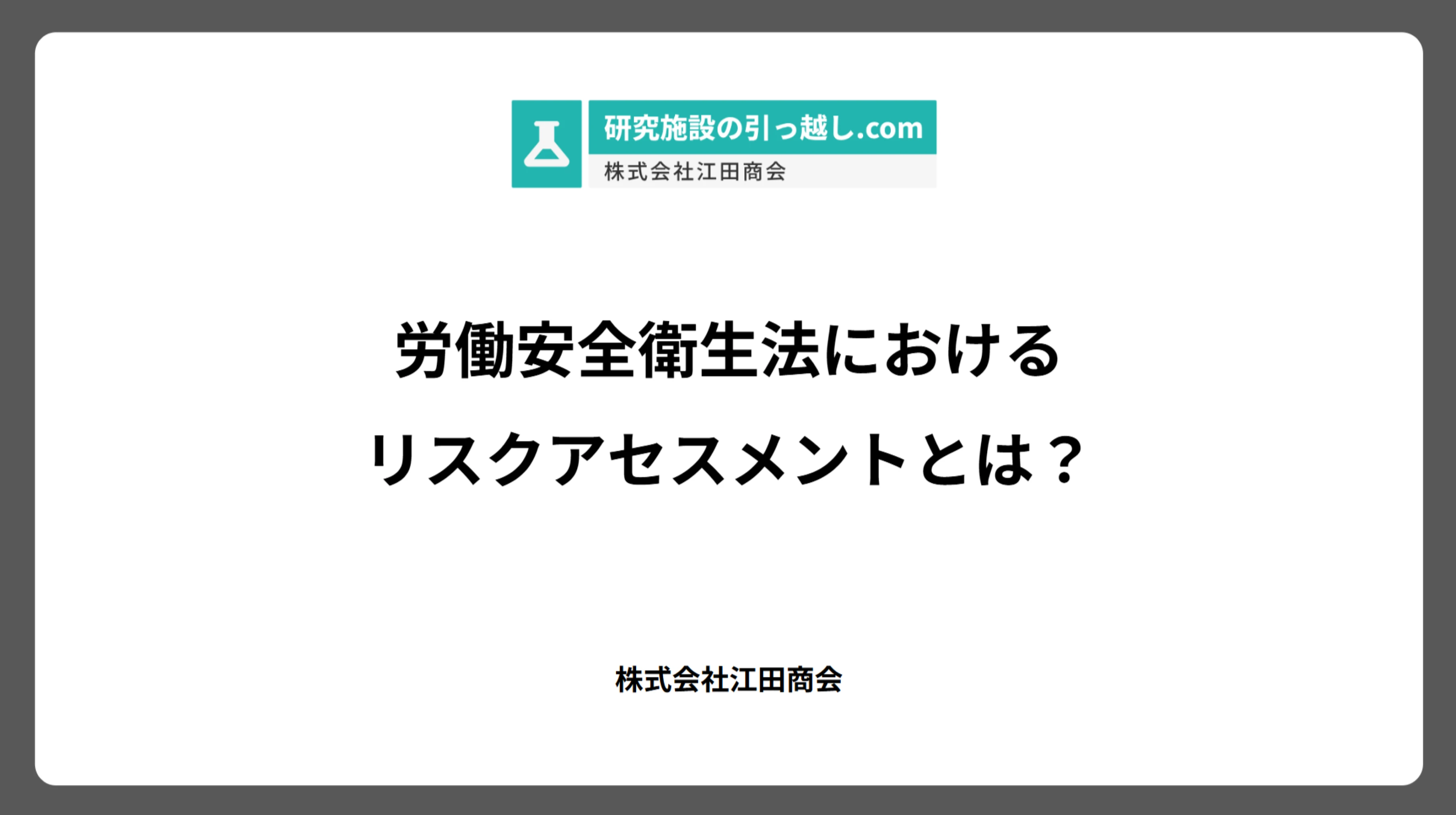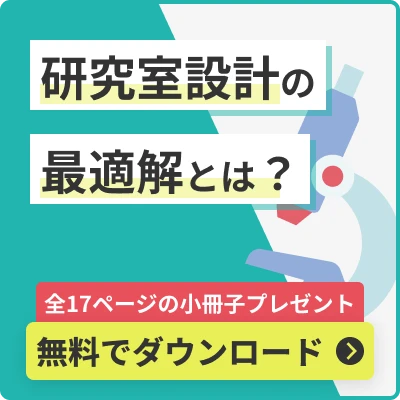記事公開日
最終更新日
研究室レイアウトのポイント10選!デスクはどう配置する?

研究室レイアウトの設計は、研究効率や安全性、コミュニケーションに大きな影響を与えます。
特に製造業や大学・大学院の研究室では、限られたスペースをいかに有効活用するかが重要な課題です。
近年では、研究機器の高性能化や作業工程の複雑化に伴い、「使いやすいレイアウト設計」が中小規模の研究施設でも求められています。
また、安全性を確保しつつ、作業効率やチーム間の連携を高めるための工夫も不可欠です。
そこで、この記事では研究室をより快適で機能的にするための「研究室レイアウトのポイント10選」をご紹介します。
研究室レイアウトを見直すべき理由
研究環境と生産性の関係
研究室のレイアウトは、日々の研究活動の「質」と「効率」を大きく左右します。たとえば、動線が整理されていない場合、頻繁な移動により時間が無駄になったり、実験中の事故リスクが高まったりすることがあります。
逆に、作業フローに沿った配置がなされていれば、必要な機材へすぐにアクセスでき、集中力を保ちながら作業を進めることが可能になります。
さらに、デスクや機器の位置関係に配慮することで、研究員同士の自然なコミュニケーションも促進され、チームとしての一体感や情報共有のスピードも向上します。
特に製造業や大学の研究現場では、限られた時間で確実な成果を求められるため、環境整備は極めて重要な経営課題の一つです。
中小企業・大学研究室特有の課題
日本の中小企業や大学研究室が直面する最大の課題は、「限られたスペースでいかに多機能かつ効率的な環境を構築するか」にあります。
研究室は設備や機器が年々増加する傾向にある一方で、建物の構造や予算の制約から拡張が難しいケースが多く見られます。
その結果、収納の不足や配線の煩雑化、作業動線の交錯など、さまざまな運用上の非効率が積み重なりやすい状況です。
また、研究室の新設や改装を担当する現場のリーダーが、建築や空間設計に詳しくないことも多いため、外部の専門支援を受けながら改善を進めることが鍵となります。
このような課題を踏まえ、研究室のレイアウトを体系的に見直すことで、限られた資源の中でも最大限のパフォーマンスを発揮する環境づくりが可能となります。
研究室レイアウトのポイント10選
①安全動線を最優先に設計する
研究室では火気や薬品、精密機器を扱うため、安全な動線設計が最も重要です。
緊急時の避難経路をふさがないように通路幅を十分に確保し、作業エリアと移動経路が交差しないように配置を工夫しましょう。
安全標識や足元表示も有効です。
②自然光や照明配置に配慮する
自然光の取り入れ方や照明の配置も、集中力や作業精度に影響します。
できるだけ窓際にデスクを配置し、陰になりやすい場所にはLEDなどで均等な明るさを確保しましょう。
目の疲れを防ぐためにも、色温度の調整が可能な照明が望ましいです。
③機器ごとの作業ゾーンを明確にする
分析機器、試薬、パソコンなどの用途別にゾーンを分けることで、混雑や誤操作を防ぎやすくなります。
機器の使用頻度や必要な作業スペースを踏まえ、使用中の人とほかの人が干渉しないレイアウトが理想です。
④デスク配置はチーム構成に応じて調整
個別作業が中心の部署ではパーティションで区切り、共同作業が多いチームでは島型配置が効果的です。
コミュニケーションの取りやすさと作業のしやすさを両立できるよう、メンバーの役割や作業内容を考慮して調整しましょう。
⑤収納は「見える化」で整頓しやすく
収納棚や引き出しは「何がどこにあるか」が一目でわかる工夫が必要です。
透明のボックスやラベル表示を活用し、使用頻度の高いものは手が届きやすい位置に配置することで、無駄な時間を削減できます。
⑥通信・電源の配線設計も重要
配線の煩雑さは転倒事故や接続トラブルの原因になります。
床下配線や配線ダクトの活用により、見た目にもすっきりとした環境が整います。
LANや電源のポート数・位置も将来の機器増設を見越して設計することが望まれます。
⑦将来の拡張性を考慮した設計
研究は変化が常であり、新しい機器の導入やレイアウト変更が必要になることも。
固定式の什器ではなく、モジュール化された移動可能な什器を活用することで、柔軟に対応できる設計が可能となります。
⑧防災・BCP対策としての配慮
自然災害時の被害を最小限に抑えるためにも、防災対策は必須です。
倒壊防止金具の取り付けや、出入口付近の障害物排除、避難経路の確保などを徹底し、事業継続計画(BCP)にも組み込んでおくことが望まれます。
⑨移動可能なレイアウトで柔軟性を確保
キャスター付きの机や棚を取り入れることで、状況に応じて配置を自由に変更できます。
作業内容やチーム編成の変更にも迅速に対応できるため、運用効率が向上します。
⑩清掃しやすい配置で衛生管理も徹底
清掃がしにくい隙間や機器下部の埃は、機械トラブルや健康リスクの要因になります。
床との隙間が少ない収納や、床面にものを置かないルールを設けることで、衛生的な環境を維持できます。
まとめ
研究室レイアウトの見直しは、単なる模様替えではなく、安全性・生産性・連携力を高める「経営的な投資」といえます。
今回ご紹介した10のポイントは、すぐに取り入れられるものから中長期的な改善に向けた視点まで幅広く網羅しています。
特に、安全動線や配線整理、将来の拡張性などは、研究環境を「変化に強いもの」にするために欠かせない視点です。
研究室の新設・移転・リニューアルといった大きなレイアウト変更を検討されている場合は、専門家のサポートを受けることも有効です。
たとえば江田商会では、研究施設の設計から施工、運用アドバイスまで一貫して支援するトータルサポートを提供しており、研究現場の課題に精通した提案が期待できます。
研究室のレイアウト改善は、一朝一夕で完了するものではありませんが、一つひとつの工夫が着実に現場を快適かつ効率的な空間へと導いてくれます。
本記事をヒントに、ぜひ貴社・貴校の研究環境の改善に取り組んでみてください。
研究室レイアウトの基本 効率と機能性を最大化するポイントとは?
研究施設の設計・移転はお任せください
分析・測定・制御機器の販売およびコンサルティングを事業展開している江田商会が、研究室の移転に伴う、研究機器・設備周りの配線や研究室デザイン、内装・設備工事など、移転に必要な作業をすべて請け負います。