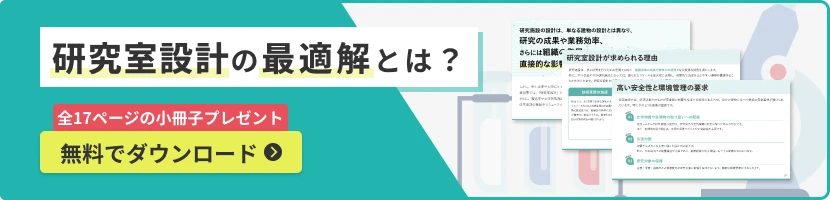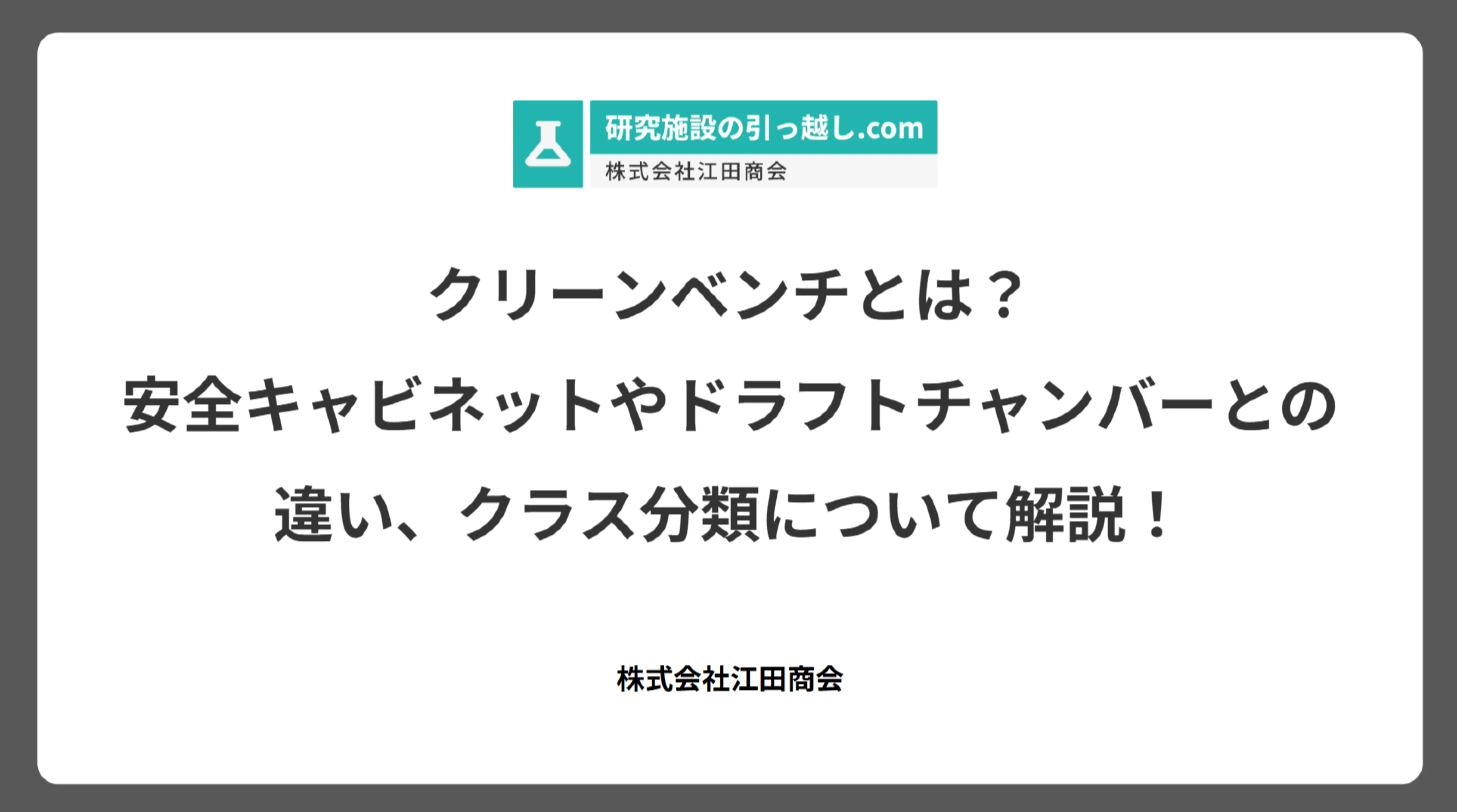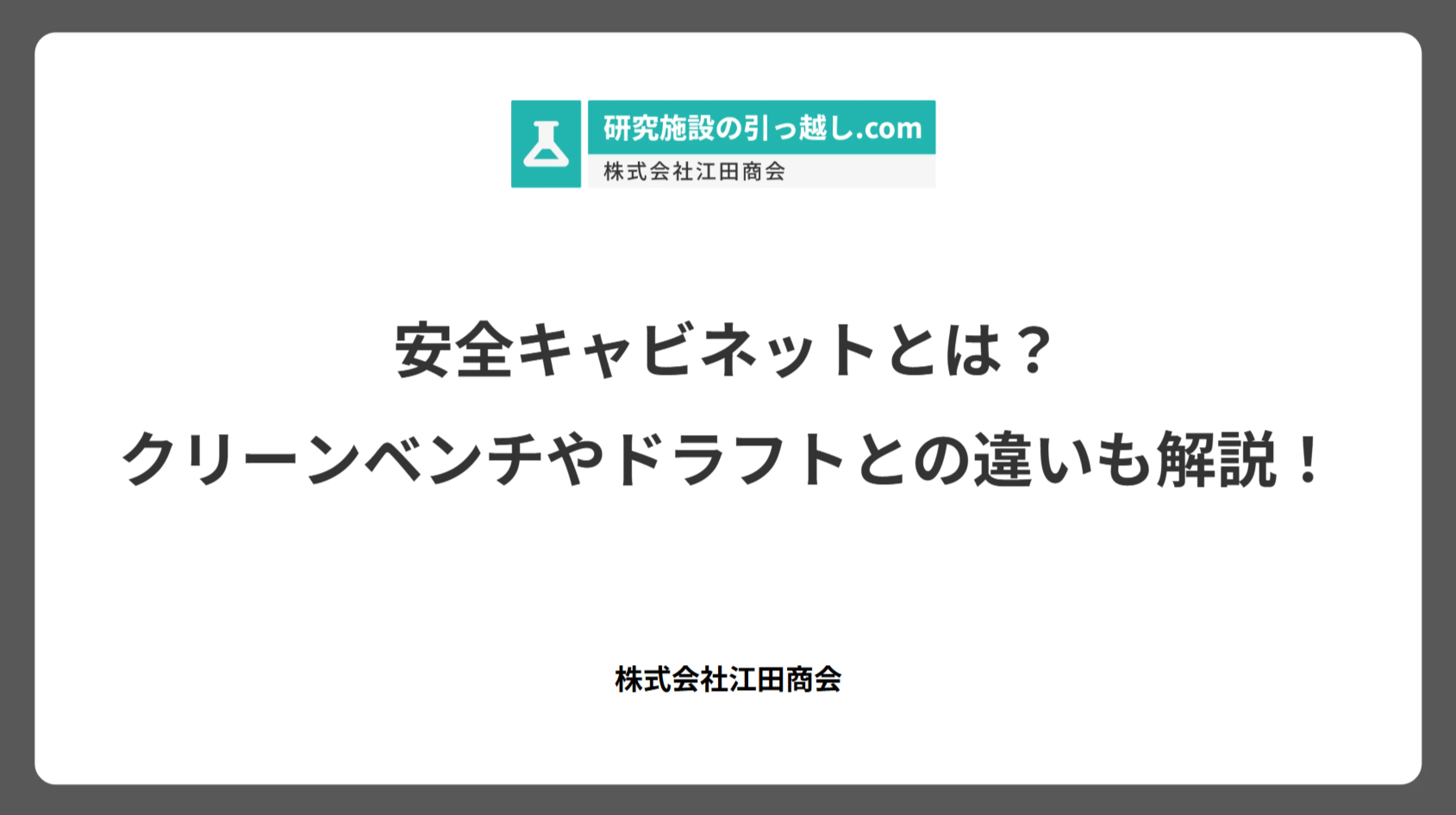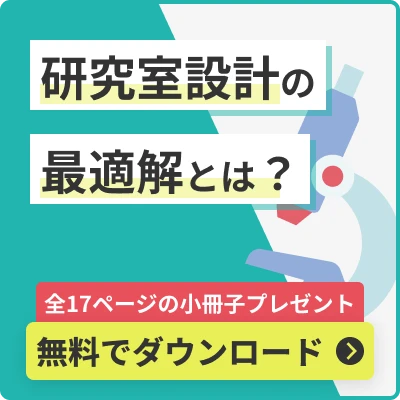記事公開日
最終更新日
化学物質リスクアセスメントのやり方とは?頻度は?法改正や義務化についても解説!

化学物質を取り扱う事業所では、そのリスクを適切に管理することが極めて重要です。
特に、中小企業の製造業や大学・大学院の研究室においては、限られたリソースの中でいかに効果的な化学物質リスクアセスメントを実施するかが課題となっています。
2024年の化学物質関連法改正により、リスクアセスメントの実施はさらに重要性を増しており、その正しいやり方や頻度、義務化のポイントを理解することが不可欠です。
そこでこの記事では、研究室長や工場長の方々が抱える疑問を解消し、実践的なリスクアセスメントのノウハウをご紹介いたします。
化学物質リスクアセスメントとは?
化学物質リスクアセスメントとは、事業場で使用する化学物質による労働者の健康障害や災害のリスクを事前に評価し、そのリスクを低減するための措置を検討・実施することです。
労働安全衛生法第57条の3に基づき、危険性または有害性のある化学物質を取り扱う事業者に義務付けられています。
化学物質リスクアセスメントの義務化は、いつから?
化学物質リスクアセスメントは、2016年6月1日から義務化されています。
さらに、2024年4月1日からは、特定の化学物質についてリスクアセスメントの結果に基づいたばく露防止措置が義務付けられるなど、法改正によってその重要性は増しています。
化学物質リスクアセスメントの対象物質一覧
化学物質リスクアセスメントの対象となるのは、労働安全衛生法で「危険物及び有害物」と定められている化学物質です。
具体的には、労働安全衛生法施行令別表第一に掲げられている爆発性、発火性、引火性などの危険物、およびがん原性、変異原性、急性毒性などの有害性が確認されている化学物質が該当します。
約670物質がリスクアセスメントの対象として指定されており、特に通知対象物と呼ばれるGHS分類で危険有害性情報が通知されている化学物質については、リスクアセスメントの実施が必須となります。
化学物質リスクアセスメントの具体的なやり方・手順
化学物質リスクアセスメントは、以下の5つのステップで実施されます。
ステップ1:GHS分類と危険有害性の特定
まず、取り扱う化学物質の危険性や有害性を特定します。
これには、SDS(安全データシート)のGHS分類情報が非常に重要です。
GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に基づき、物質の引火性、爆発性、毒性、発がん性などを確認します。
SDSが手元にない場合は、メーカーや供給業者に確認し、最新の情報を入手することが重要です。
ステップ2:ばく露濃度の測定・推定
次に、労働者が化学物質にどの程度さらされる可能性があるか(ばく露濃度)を測定または推定します。
作業環境測定の結果があればそれを活用できますが、ない場合は作業内容、換気状況、取扱量などを考慮して推定します。
厚生労働省が提供している「化学物質のリスクアセスメント実施支援システム」などを活用することで、簡易的にばく露濃度を推定することも可能です。
ステップ3:リスクの見積もり
ステップ1で特定した危険有害性と、ステップ2で推定したばく露濃度を組み合わせて、リスクの程度を見積もります。
これは、たとえば「危険性が高く、ばく露濃度も高い場合は高リスク」といったかたちで評価します。
リスクの見積もり方法には、厚生労働省が推奨する「コントロール・バンディング」手法などがあります。
これは、化学物質の危険有害性と取扱量や揮発性などを考慮して、リスクレベルを簡易的に評価するものです。
ステップ4:リスク低減措置の検討と実施
見積もられたリスクに応じて、リスクを低減するための措置を検討し、実施します。
リスク低減措置は、以下の優先順位で検討することが推奨されます。
- 本質的対策(排除・代替)…有害性の低い化学物質への代替や、有害な化学物質を使用しない工程への変更など。
- 工学的対策(設備改善)…局所排気装置の設置、密閉化、自動化など。
- 管理的対策(作業方法の改善)…作業手順書の作成、休憩時間の確保、入退室管理など。
- 個人用保護具(PPE)…保護手袋、保護メガネ、呼吸用保護具の着用など。
ステップ5:結果の記録と周知
リスクアセスメントの結果、検討したリスク低減措置の内容、実施状況などを記録します。
この記録は、労働安全衛生規則に基づき、一定期間保管する義務があります。
また、リスクアセスメントの結果や実施した措置については、関係する労働者全員に周知徹底することが求められます。
これにより、労働者自身もリスクを理解し、安全な作業を心がけることができます。
化学物質リスクアセスメントの実施頻度と見直しのタイミング
定期的な実施の必要性
化学物質リスクアセスメントは、一度行えば終わりではありません。
定期的に見直しを行い、常に最新の状態を保つことが重要です。
具体的な頻度は法令で定められていませんが、一般的には年に1回程度の定期的な見直しが推奨されます。
見直しが必要となるケース
以下のような場合には、定期的な見直しとは別に、速やかにリスクアセスメントを実施し直す必要があります。
- 新規の化学物質を導入する場合
- 既存の化学物質の取扱量や使用方法を変更する場合
- 作業工程や設備の変更を行う場合
- 労働者から健康被害の訴えがあった場合
- 関連法規の改正があった場合
- 過去のリスクアセスメントの結果、改善が必要と判断された場合
記録の保存と管理
リスクアセスメントの記録は、実施日、対象物質、リスク評価結果、低減措置の内容、担当者などを明確に記載し、適切に保管することが義務付けられています。
労働安全衛生規則第34条の2の9に基づき、3年間保存する必要があります。
これらの記録は、労働基準監督署からの指導や調査の際に提示を求められることがありますので、整理して保管しておくことが重要です。
中小企業・大学がリスクアセスメントを効果的に進めるためのポイント
中小企業や大学・大学院の研究室では、専門人材の不足や予算の制約などから、リスクアセスメントの実施に困難を感じるケースも少なくありません。
しかし、以下のポイントを押さえることで、効果的にリスクアセスメントを進めることが可能です。
専門家や外部サービスの活用
自社に専門知識を持つ人材がいない場合は、労働衛生コンサルタントや産業医などの専門家、あるいはリスクアセスメントのコンサルティングサービスを提供している外部機関の活用を検討しましょう。
厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」でも、専門機関の紹介や支援に関する情報が提供されています。
簡易的なアセスメントツールの活用
厚生労働省が提供している「化学物質のリスクアセスメント実施支援システム(CREATe Simple)」や、各種団体が開発している簡易アセスメントツールなどを活用することで、専門知識がなくても比較的容易にリスクアセスメントを実施できます。
これらのツールは、特に中小企業向けに開発されており、リスク評価から低減措置の検討までをサポートしてくれます。
従業員への教育と周知徹底
リスクアセスメントは、担当者だけで完結するものではありません。
化学物質を取り扱うすべての従業員がリスクの重要性を理解し、安全な作業方法を実践することが不可欠です。
定期的な安全衛生教育を実施し、リスクアセスメントの結果や講じられた措置について周知徹底を図りましょう。
安全衛生管理体制の整備
リスクアセスメントを継続的に実施し、効果を最大化するためには、組織としての安全衛生管理体制を整備することが重要です。
安全衛生推進者の選任、安全委員会の設置、責任範囲の明確化などを行い、PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回しながら、継続的な改善を図っていくことが求められます。
まとめ
化学物質リスクアセスメントは、労働者の安全と健康を守り、事業活動を継続していく上で不可欠な取り組みです。
特に、2024年の法改正により、その重要性はさらに増しています。
中小企業の製造業や大学・大学院の研究室においては、リソースが限られる中でも、本記事でご紹介した具体的なやり方や効果的に進めるためのポイントを参考に、積極的にリスクアセスメントに取り組んでいただくことをおすすめします。
安全で健康な職場環境を実現し、企業の持続的な発展に繋げていきましょう。
化学物質管理者の義務化とは?2024年4月からの対象・選任・罰則を解説!
研究施設の設計・移転はお任せください
分析・測定・制御機器の販売およびコンサルティングを事業展開している江田商会が、研究室の移転に伴う、研究機器・設備周りの配線や研究室デザイン、内装・設備工事など、移転に必要な作業をすべて請け負います。