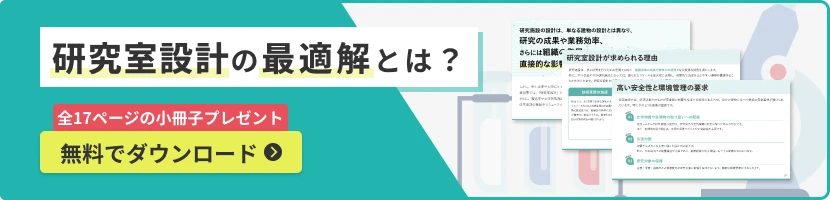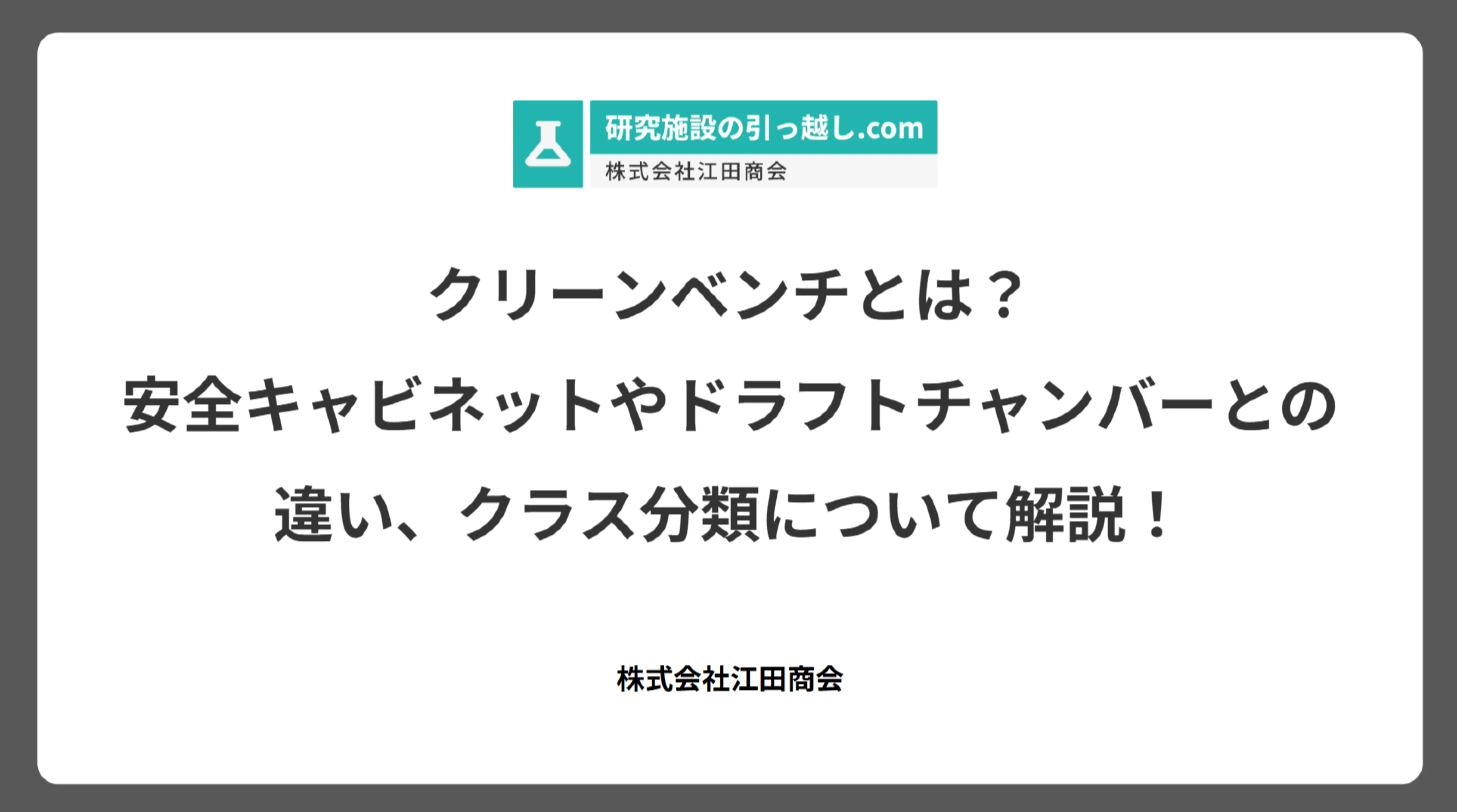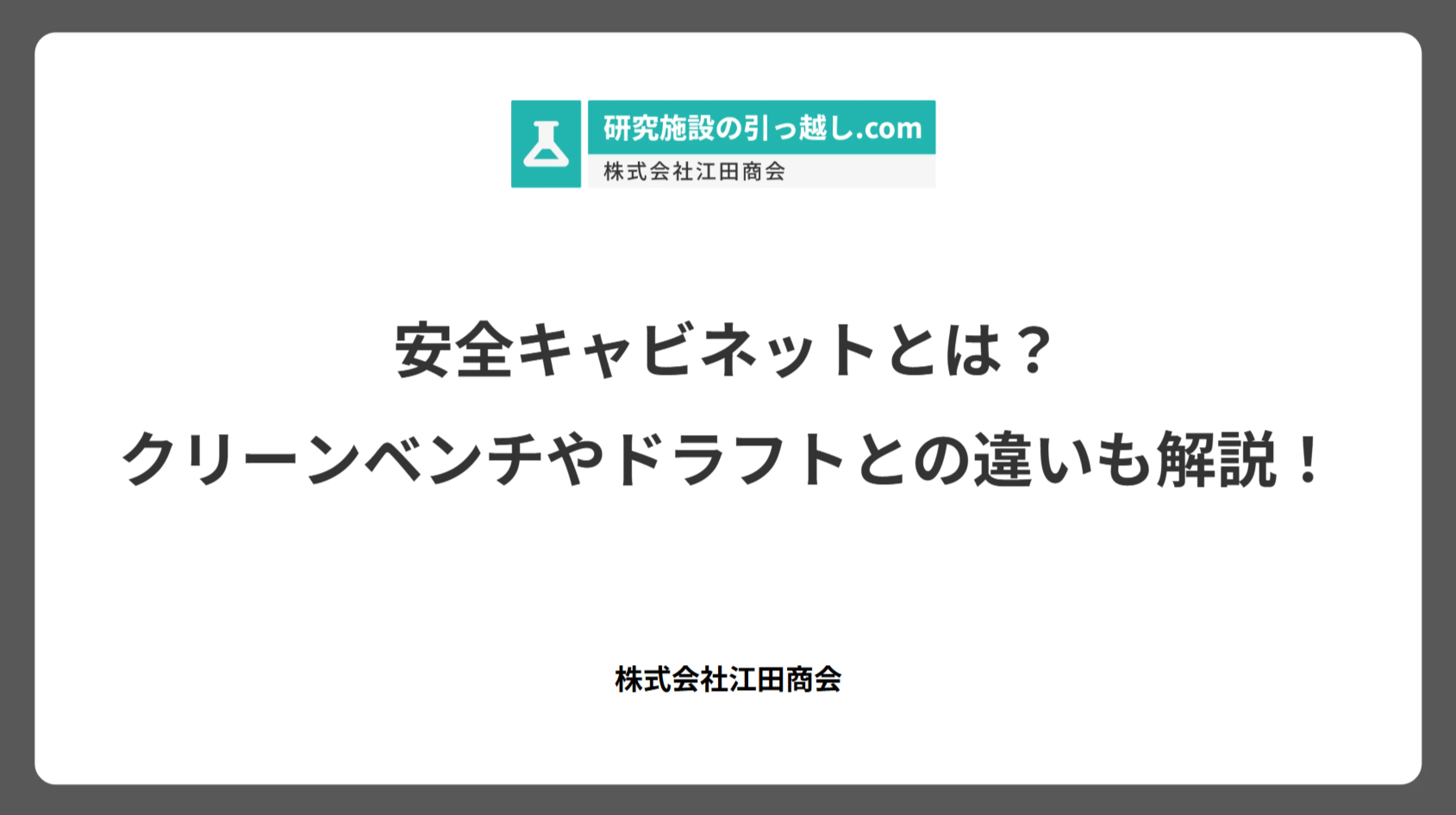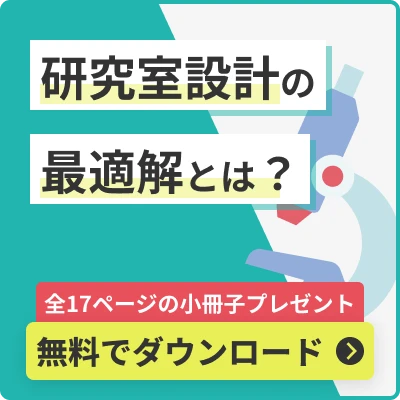記事公開日
最終更新日
建築基準法で定める研究施設の用途区分とは?建築基準法の規定をわかりやすく解説

研究施設の建設や改修を検討する際に重要なのが、建築基準法における用途区分です。 特に、製造業の研究開発部門や大学・大学院の研究室長、工場長にとって、適切な用途区分を理解することは、スムーズな計画立案に不可欠です。
建築基準法では、建物の用途を明確に定めており、研究施設もその対象に含まれます。研究施設の用途区分を誤ると、行政手続きの遅延や計画の見直しを余儀なくされる可能性があります。
そこで本記事では、建築基準法における研究施設の用途区分について、適用範囲や注意点をわかりやすく解説します。
研究施設の用途区分とは?
研究施設は、製造業の研究開発部門や大学・大学院の研究室にとって不可欠な存在です。 しかし、建築基準法においては、その用途が厳密に定められており、適用される規定を正しく理解することが重要です。用途区分を誤ると、建設許可の取得が困難になったり、後の用途変更が必要になったりする可能性があります。
本章では、研究施設の用途区分の概要と、どのような建築基準法上の制約があるのかを解説します。
建築基準法における「用途区分」の基本
建築基準法では、建物の用途に応じた規制が定められています。 これは、都市の安全性や利便性を確保し、適切な土地利用を促進するためです。
建築物の用途は、大きく次のように分類されます。
- 住居系(例:住宅、共同住宅、寄宿舎など)
- 商業系(例:オフィス、店舗、飲食店など)
- 工業系(例:工場、倉庫、研究施設など)
研究施設は、一般的に「工業系」または「特殊建築物」に該当します。 ただし、大学・大学院の研究室などは「教育施設」として分類されることもあります。
研究施設が該当する用途区分
研究施設の用途区分は、研究の内容や施設の規模、地域の用途指定によって異なります。
以下に、主な用途区分を示します。
工業地域・準工業地域における研究施設
製造業の研究開発を目的とした施設は、多くの場合「工業地域」または「準工業地域」に設置可能です。
ただし、排出物の管理(有害物質・騒音など)が必要な場合があるため、環境基準を満たすことが求められます。
商業地域・近隣商業地域における研究施設
商業地域でも、特定の用途(バイオ・医薬品開発など)に限定された研究施設は許可されることがあります。
ただし、大型の研究施設(特に実験設備を伴うもの)は、適合しないケースが多いです。
文教地区・大学キャンパス内の研究施設
大学や研究機関内の施設は、教育目的とみなされ、「文教地区」や「特定用途地域」での建設が可能です。
ただし、商業的な研究(企業との共同研究施設など)の場合は、別の用途として分類される場合があります。
研究施設の建設時の注意点
研究施設の建設を検討する際、建築基準法の適用や用途区分、施設の設計に関する重要なポイントを事前に理解しておくことが不可欠です。 適切な準備を行わないと、許認可手続きの遅れや追加コストの発生、施設の用途変更が必要になるリスクがあります。
本章では、研究施設の建設における主要な注意点を解説します。
建築基準法における研究施設の適用範囲を確認する
研究施設には、建築基準法に基づき、建設可能な地域や用途区分が定められています。 施設を計画する際は、事前に自治体の都市計画や用途地域の確認を行うことが重要です。
研究施設に適した用途地域とは?
用途地域によって、研究施設の建設可否や制限が異なります。
以下のように、用途地域ごとに研究施設の適用が異なります。
| 用途地域 | 研究施設の適用範囲 |
| 工業地域 | ほぼ制限なし。大規模研究施設も建設可能 |
| 準工業地域 | 一般的な研究施設は建設可能だが、化学・医薬系は制限あり |
| 商業地域 | 小規模な研究施設は可。ただし、騒音・振動の規制あり |
| 文教地区 | 大学・研究機関の研究施設は可能。企業の研究施設は不可の場合も |
このように、建設予定地の用途地域が、研究施設の用途に適合しているかどうかを確認することが必須です。
設備と安全基準の適用に注意する
研究施設には、通常のオフィスや工場とは異なる特有の設備要件や安全基準が求められます。 特に、化学実験や高度な研究を行う施設では、厳しい基準が適用されることがあります。
火災・災害対策
■消防法による防火・防爆設備の設置
研究施設内で可燃性ガスや化学物質を使用する場合、防爆構造や耐火壁の設置が必要となるケースがあります。
■避難経路と非常時対策
一定規模以上の施設では、複数の避難経路を確保することが義務付けられています。 また、非常用発電機や換気装置の設置も推奨されます。
環境基準・排出物管理
■有害物質の排出管理
研究施設で化学薬品を使用する場合、廃棄物や排水の処理基準を満たす必要があります。 特に、工業地域外に立地する場合は、排水規制が厳しくなるため、自治体の規定を事前に確認しましょう。
■騒音・振動規制
精密機器を使用する研究施設では、騒音・振動の管理が求められることがあります。 特に、住宅地や商業地域に近い施設では、防音壁や免震構造の設計が必要となることもあります。
研究設備の設置に関するポイント
研究施設は、設置する設備によって建物の構造や設計に影響を及ぼします。 特に、以下のポイントに注意が必要です。
研究機器の重量と建物構造
電子顕微鏡・精密測定機器など、重量のある機器を設置する場合、床の耐荷重設計を適切に行う必要があります。 耐震設計の強化が求められるケースもあり、設備配置を考慮したレイアウトが重要です。
電源・配線設備
安定した電源供給の確保が不可欠であり、特に医薬・バイオ研究施設では、停電時のバックアップ電源(UPSや非常用発電機)が求められることがあります。 クリーンルームを設置する場合、電磁波対策や静電気防止対策が必要です。
換気・空調設備
化学実験を行う施設では、有害ガスや微粒子の管理が必要となるため、排気ダクトや換気システムの設計が重要です。 研究施設においては、温度・湿度管理が精密に求められることがあり、特殊空調システムの導入が必要になるケースもあります。
建築計画・許認可手続きの確認
研究施設の建設には、建築基準法の規定に基づいた各種手続きが必要になります。 特に、以下の点を事前にチェックしておきましょう。
建築確認申請
一定規模以上の研究施設を新築・増築する場合、建築確認申請が必要になります。 用途変更を伴う建設(例:倉庫を研究施設に転用する場合)も、新たに申請が求められることがあります。
環境影響評価(EIA)の確認
研究施設の排水や排気の影響を事前に評価し、必要に応じて環境影響評価の提出が求められます。
自治体ごとの条例の確認
各自治体で独自の建築基準条例や環境規制があるため、事前に確認が必要です。
研究施設の用途区分変更に関するポイント
研究施設の運用を続ける中で、施設の用途を変更する必要が生じるケースは少なくありません。 たとえば、製造業の研究開発施設が、新たに製造プロセスを伴う試作工場へと用途変更する場合や、大学の研究室が企業と連携し、産学共同の研究開発拠点として機能を拡張する場合などが考えられます。
しかし、建築基準法においては、建物の用途を変更する場合に厳格な規制が適用されるため、事前に必要な手続きや条件を理解しておくことが重要です。
本章では、研究施設の用途区分変更に関するポイントについて解説します。
用途区分変更とは?
用途区分変更とは、建築物の用途を、建築基準法で定められた異なる用途に変更することを指します。
たとえば、以下のような変更が用途区分変更に該当します。
研究施設に関する代表的な用途変更の例
| 変更前 | 変更後 | 例 |
| 研究施設(実験・解析のみ) | 研究開発+試作工場 | 製造業のR&D部門が試作品製造を開始 |
| 大学の研究室 | 企業と共同研究施設 | 産学連携による新規プロジェクトの開始 |
| 一般オフィス | 研究施設 | オフィスビルの一部を研究用途に転用 |
| 倉庫 | 研究施設 | 物流拠点を実験施設へリノベーション |
これらの用途変更を行う場合、建築基準法に適合するかどうかを事前に確認し、必要な手続きを適切に進めることが求められます。
用途区分変更に必要な手続き
用途区分変更を行う場合、建築基準法に基づく建築確認申請が必要となるケースが多くあります。
手続きの流れを理解し、スムーズに進めるためのポイントを押さえましょう。
建築確認申請の要否を確認する
用途変更に際して建築確認申請が必要かどうかは、変更の内容によって異なります。 一般的に、以下の基準に該当する場合は、建築確認申請が必要です。
■建築基準法第6条に基づく建築確認申請が必要なケース
- 主要構造部分に変更がある場合(例:耐火性能の向上が必要な場合)
- 異なる用途区分に変更する場合(例:倉庫→研究施設)
- 防火・避難規制が変更される場合(例:人の収容人数が大幅に増加する場合)
一方で、同じ用途区分内での軽微な変更であれば、建築確認申請が不要となる場合もあります。 たとえば、研究施設の内部レイアウト変更や、設備の更新などは、建築確認申請が不要となることが多いです。
自治体への事前相談
研究施設の用途変更を検討する際には、まず自治体の建築指導課などに相談することが推奨されます。
用途地域の規制を確認し、変更後の用途が該当地域で認められるかどうかを調査することが重要です。
必要な書類の準備
用途区分変更に関する申請では、以下のような書類が求められることが一般的です。
| 必要書類 | 内容 |
| 建築確認申請書 | 用途変更に関する基本情報 |
| 設計図書 | 新たな用途に適合した建築計画 |
| 防火・避難計画 | 避難経路や防火設備の整備状況 |
| 環境影響評価 | 廃棄物処理・騒音規制など |
用途区分変更における注意点
用途変更を行う際には、以下の点に特に注意する必要があります。
防火・避難基準の適合
研究施設では、使用する設備や実験環境によって、防火・避難計画の見直しが必要となることがあります。
たとえば、
- 化学薬品を使用する場合:排気システムの改修、防爆設備の追加が必要
- 研究員の人数が増える場合:避難経路の確保、消火設備の強化が求められる があります。
環境基準の適用
研究施設が新たな用途に変更されることで、環境影響評価(EIA)が必要となるケースがあります。 特に、排水や廃棄物処理が強化される場合、環境基準に適合した設備の導入が求められます。
用途変更によるコスト増加
用途変更には、建築確認申請費用、設備改修費用、行政手続きのコストが発生します。 特に、変更後の用途に応じた耐震補強や断熱改修が必要になる場合、想定以上のコストがかかることがあります。
まとめ
研究施設の建設や改修を進める際には、建築基準法の用途区分を正しく理解し、適切な計画を立案することが不可欠です。用途区分の誤解や適用ミスは、行政手続きの遅延や施設の再設計を招くリスクがあるため、事前の調査と準備が非常に重要です。
研究施設の用途区分を理解し、建築基準法の規制を適切にクリアすることが、安全で効率的な研究環境の実現につながります。事前の調査と専門家のサポートを活用しながら、スムーズな施設計画を進めましょう。
研究機関登録の方法とは?メリットと申請方法をわかりやすく解説
研究施設の設計・移転はお任せください
分析・測定・制御機器の販売およびコンサルティングを事業展開している江田商会が、研究室の移転に伴う、研究機器・設備周りの配線や研究室デザイン、内装・設備工事など、移転に必要な作業をすべて請け負います。