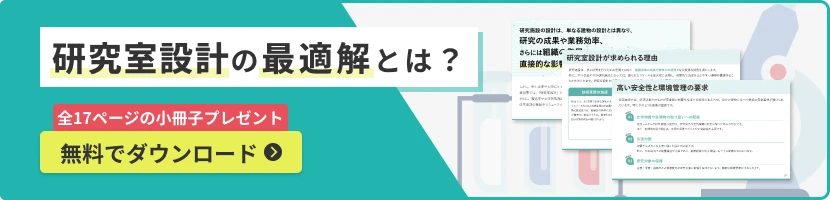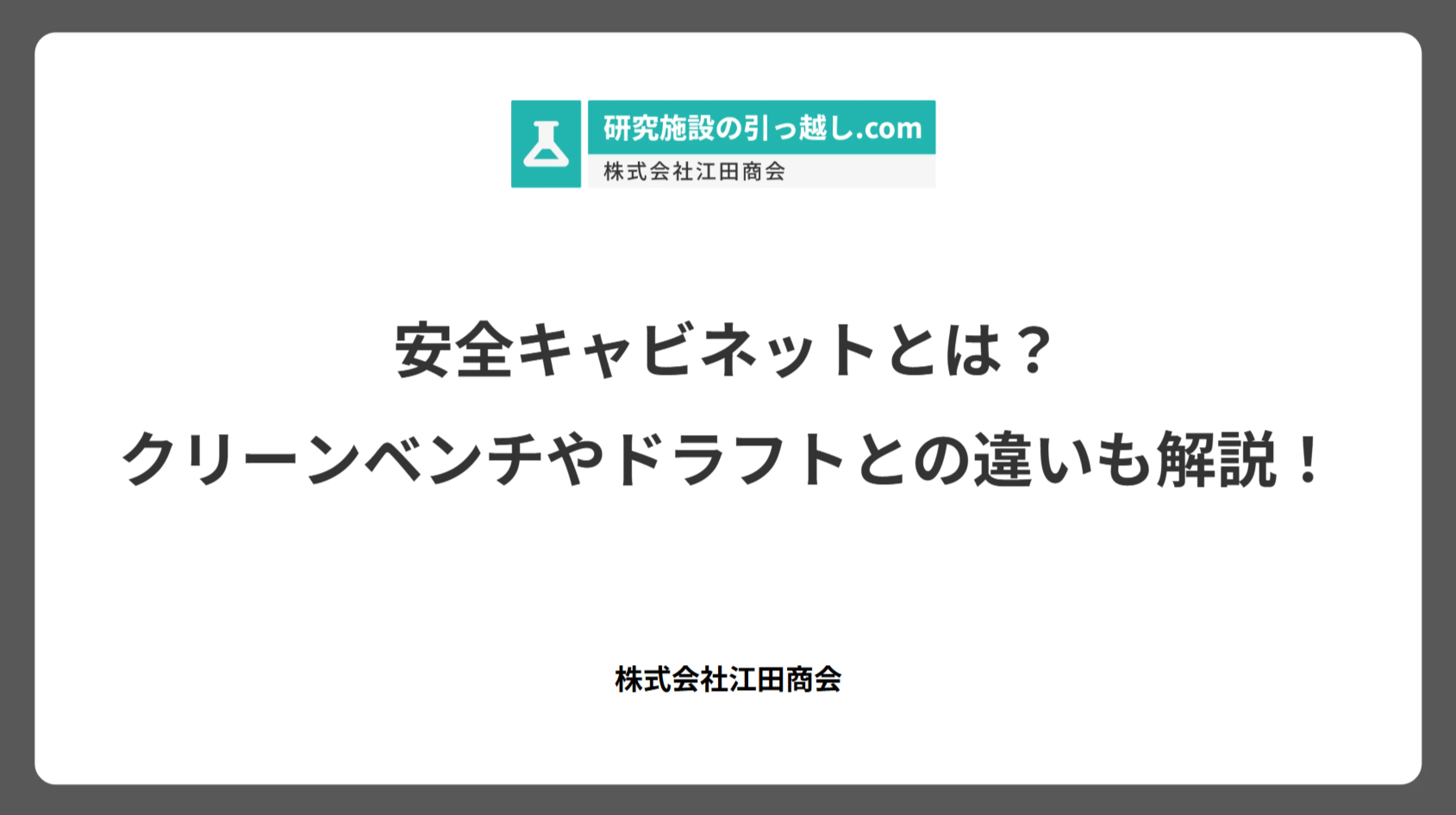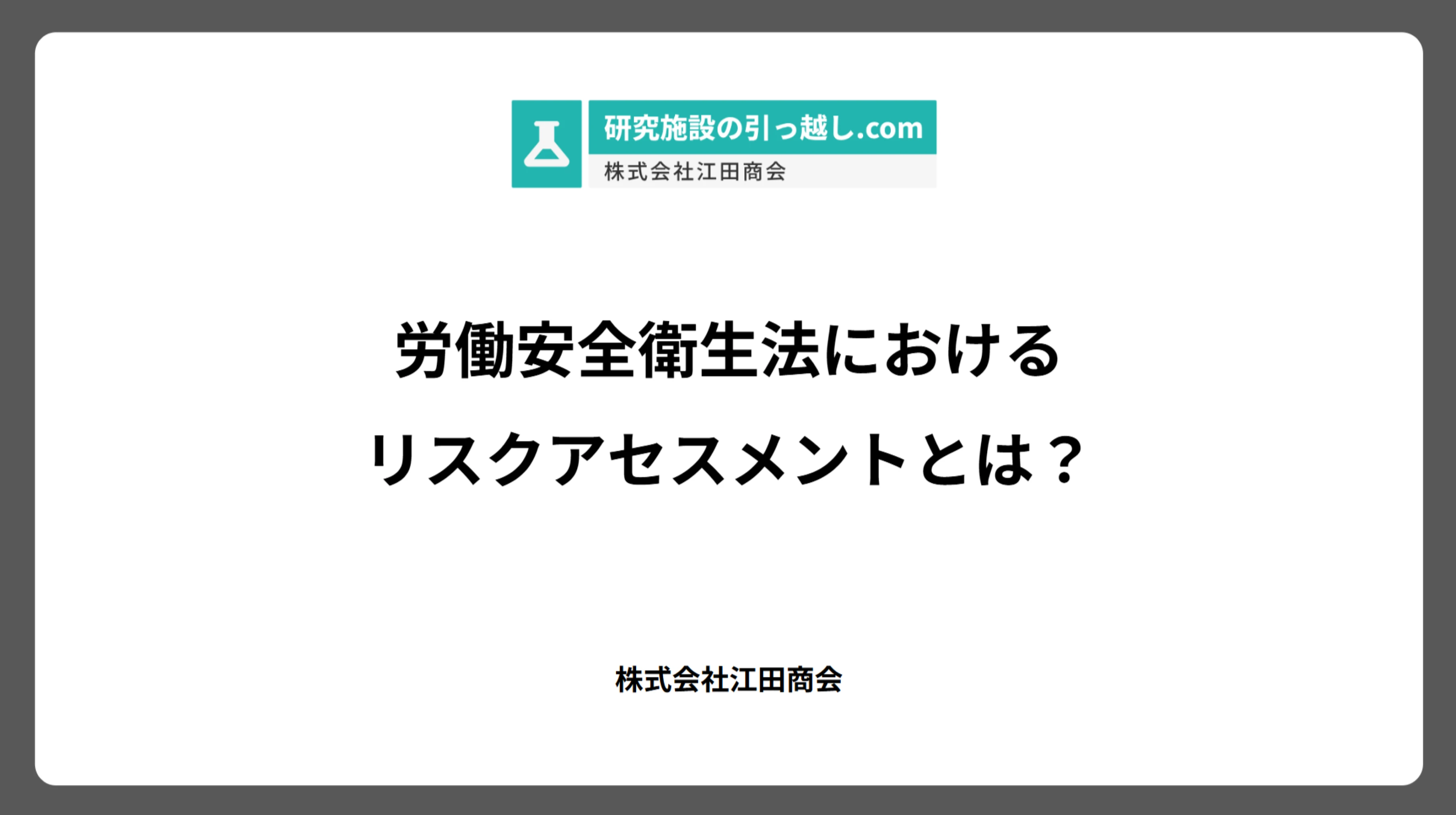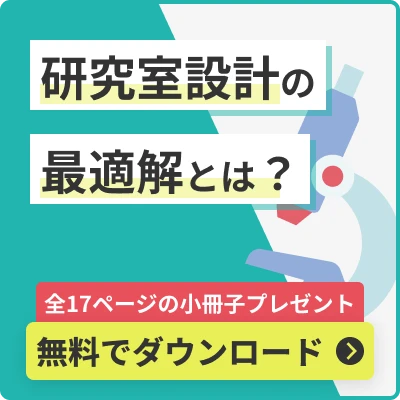記事公開日
化学物質管理者の義務化とは?2024年4月からの対象・選任・罰則を解説!
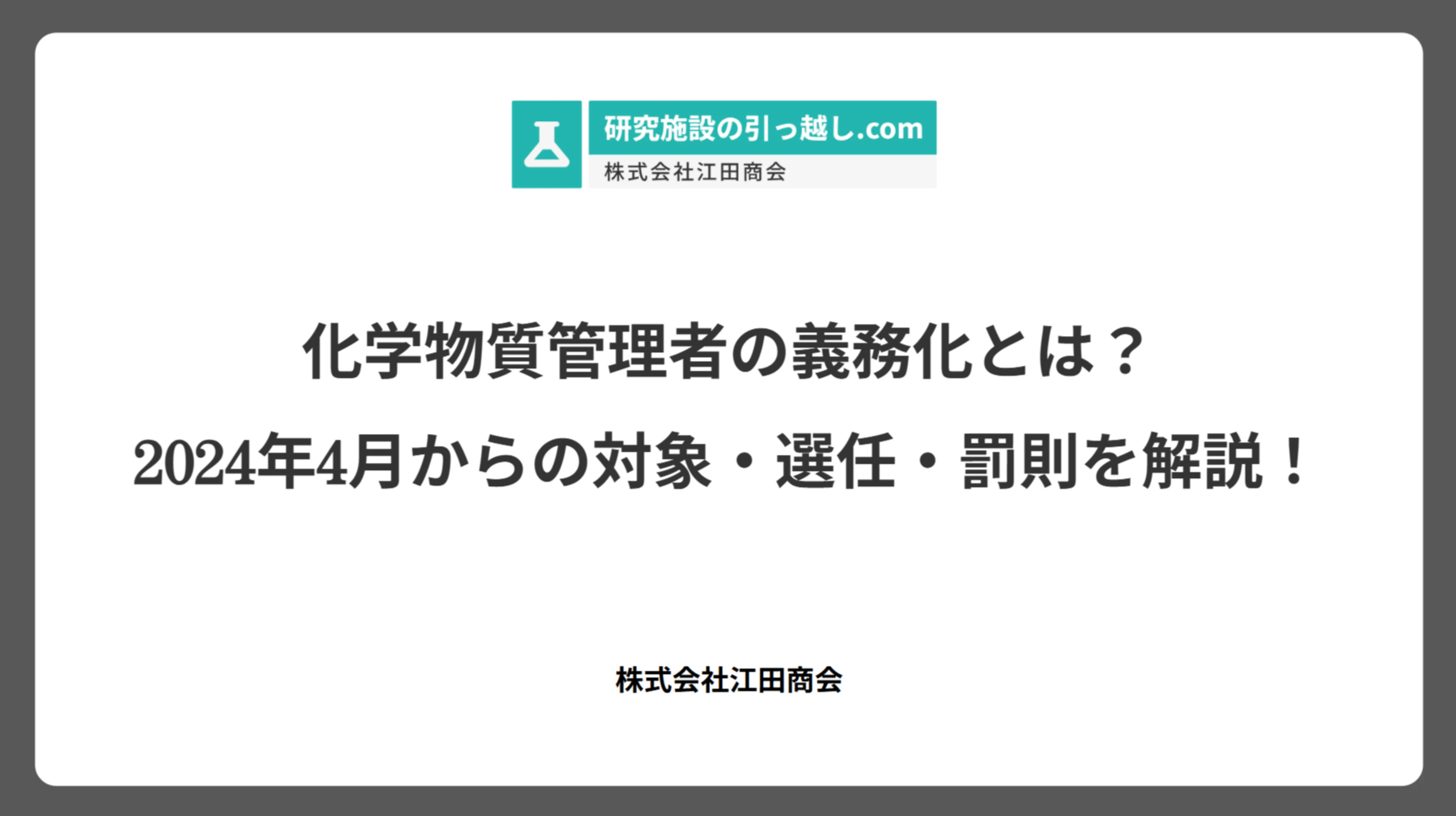
2024年4月から労働安全衛生法の改正により、化学物質管理者の選任が義務化されました。
製造業の工場長や研究室長の皆様にとって、この新たな義務化への対応は急務となっています。
しかし、「具体的に何をすればよいのか」「どんな人を選任すべきか」「違反した場合の罰則は?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。
本記事では、化学物質管理者義務化の背景から選任要件、具体的な業務内容、罰則まで、中小企業の現場で実際に対応が必要な内容を分かりやすく解説します。
適切な対応により、従業員の安全確保と法令遵守を両立させましょう。
化学物質管理者の義務化とは?2024年4月施行の背景
2024年4月1日、労働安全衛生法の一部改正により、化学物質管理者の選任が義務化されました。
この改正は、化学物質を取り扱う事業場における労働者の健康障害を防止し、より安全な職場環境を構築することを目的としています。
労働安全衛生法改正の経緯
これまでも化学物質による労働災害は後を絶たず、特にリスクアセスメントの実施は努力義務とされてきました。
しかし、化学物質による健康障害が依然として多く発生している現状を受け、国はより実効性のある対策を講じる必要性を認識しました。
2022年5月には労働安全衛生規則等の一部が改正され、その中で化学物質管理者の選任義務が新たに盛り込まれ、2024年4月からの施行となりました。
これは、事業場における化学物質管理を専門的な知見を持つ者に任せ、計画的かつ継続的に実施していくための重要な一歩です。
化学物質による労働災害の現状
厚生労働省の統計によると、毎年多くの労働者が化学物質に起因する健康障害に見舞われています。
特に、がんや皮膚炎、呼吸器疾患など、長期にわたる健康被害を引き起こすケースも少なくありません。
これらの災害は、適切な管理体制の不備や、リスクアセスメントの不徹底が原因となることが多く、事業場にとって大きなリスクとなっていました。
製造業の工場や大学の研究室では、多種多様な化学物質が扱われるため、そのリスクは一層、高まります。
義務化は、こうした現状を改善し、労働者の命と健康を守るための喫緊の課題への対応策といえるでしょう。
義務化の目的と効果
化学物質管理者の義務化の主な目的は、以下の2点です。
労働者の健康障害防止
専門知識を持つ管理者が中心となり、化学物質のリスクを適切に評価し、ばく露防止措置を徹底することで、労働災害の発生を未然に防ぎます。
事業場の化学物質管理体制の強化
法令遵守はもちろんのこと、より計画的かつ体系的な化学物質管理を推進し、安全文化を醸成します。
これにより、企業は法令違反のリスクを低減し、従業員は安心して働ける環境を得ることができます。
結果として、企業の生産性向上や社会的信用の獲得にも繋がると期待されています。
化学物質管理者の選任義務がある事業場
すべての事業場に化学物質管理者の選任義務があるわけではありません。
選任義務の対象となるのは、特定の条件を満たす事業場です。
リスクアセスメント対象物質を取り扱う事業場
化学物質管理者の選任が義務付けられるのは、リスクアセスメント対象物質を製造、または取り扱う事業場です。
具体的には、労働安全衛生法第57条の2第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める「危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を行うべき化学物質」を対象とします。
これらの物質は、労働者に危険または健康障害を生じさせるおそれのある物質として指定されています。
リスクアセスメント対象物質を製造する事業場
上記に加え、特に以下の事業場では、化学物質管理者の選任が必須となります。
- リスクアセスメント対象物質を製造する事業場
- リスクアセスメント対象物質を輸入する事業場
- リスクアセスメント対象物質を譲渡・提供する事業場
- リスクアセスメント対象物質を取り扱う事業場(研究開発を含む)
製造業の工場はもちろん、大学の研究室で実験的に化学物質を合成したり、特定の化学物質を大量に保管・使用したりする場合も対象となる可能性が高いです。
自社の事業内容と取り扱い物質を改めて確認することが重要です。
対象となる化学物質の具体例
通リスクアセスメント対象物質は、数百種類に及びます。
具体的な物質名は、厚生労働省のウェブサイトや、化学物質の安全データシート(SDS)で確認することができます。
一般的に、以下のような性質を持つ化学物質が含まれます。
- 発がん性物質: ベンゼン、アスベストなど
- 変異原性物質: 特定の有機溶剤など
- 生殖毒性物質: 特定の重金属化合物など
- 皮膚腐食性物質: 強酸、強アルカリなど
- 呼吸器感作性物質: イソシアネートなど
- 急性毒性物質: シアン化合物など
工場長や研究室長は、まず自社・自研究室で取り扱っている化学物質のSDSを全て確認し、リスクアセスメント対象物質に該当するかどうかを判断する必要があります。
SDSには、その物質の危険性・有害性情報が詳細に記載されています。
化学物質管理者の選任要件と資格
化学物質管理者には、その職務を適切に遂行するための知識と経験が求められます。
誰でも選任できるわけではないため、適切な人材を選定することが重要です。
必要な知識・経験要件
化学物質管理者に求められる知識・経験は、大きく分けて以下の通りです。
化学物質の危険性・有害性に関する知識
各化学物質の物理化学的性質、毒性、健康影響などを理解していること。
リスクアセスメントの実施能力
化学物質による危険性・有害性を特定し、リスクを評価し、適切な低減措置を検討・実施できること。
ばく露防止措置に関する知識
局所排気装置、保護具、作業方法の改善など、ばく露を防止するための具体的な措置に関する知識。
労働安全衛生法規に関する知識
化学物質に関する法令、規則、指針などを理解し、遵守できること。
緊急時対応に関する知識
化学物質漏洩や火災発生時の適切な対応、応急処置に関する知識。
これらの要件は、事業場の規模や取り扱う化学物質の種類・量によって異なりますが、専門的な知見が不可欠です。
推奨される資格・講習
特定の資格が必須とされているわけではありませんが、厚生労働省は、化学物質管理者としての知識・経験を習得するための講習の受講を推奨しています。
特に以下の講習が有効です。
化学物質管理者講習
厚生労働省が定めるカリキュラムに沿った講習で、化学物質管理に必要な知識を体系的に学ぶことができます。多くの登録教習機関で実施されています。
作業環境測定士
作業環境中の有害物質濃度を測定・評価する専門家で、化学物質管理における重要な役割を担います。
労働衛生コンサルタント
労働者の健康管理に関する専門家で、化学物質管理を含む労働衛生全般について指導・助言が可能です。
これらの資格や講習は、選任された化学物質管理者が自信を持って業務を遂行し、事業場の安全管理体制を強化する上で非常に有効です。
選任手続きと届出方法
化学物質管理者を選任した場合、労働基準監督署への届出は不要です。
しかし、以下の対応が必要です。
事業場内での選任
事業者は、上記の要件を満たす者を化学物質管理者として選任します。
氏名の周知
選任した化学物質管理者の氏名を、事業場内の見やすい場所に掲示するなどして、すべての労働者に周知する必要があります。
記録の保存
選任した年月日、氏名、職務内容などを記録し、適切に保存しておくことが望ましいです。
選任後も、化学物質管理者が継続的に知識を更新し、実務に活かせるよう、研修機会の提供など、事業者のサポートが重要となります。
化学物質管理者の具体的な業務内容
化学物質管理者の主な職務は、事業場における化学物質のリスクを管理し、労働者の安全と健康を守ることです。
その業務は多岐にわたります。
安全データシート(SDS)の管理・交付
化学物質管理者は、取り扱うすべての化学物質のSDS(Safety Data Sheet)を適切に管理する責任があります。
SDSには、化学物質の名称、成分、危険性・有害性、安全な取り扱い方法、緊急時の措置などが記載されています。
SDSの入手・更新
新しい化学物質を導入する際は必ずSDSを入手し、法改正や情報更新があった場合は最新版に差し替えます。
SDSの周知
労働者がいつでもSDSを確認できるよう、保管場所を明確にし、必要に応じて内容を説明します。
ラベル表示の確認
容器や包装に表示されているラベルがSDSの内容と一致しているかを確認し、適切な表示がされているかを監督します。
リスクアセスメントの実施・管理
化学物質管理者の最も重要な業務の一つが、リスクアセスメントの実施と管理です。
リスクアセスメントの計画・実施
取り扱う化学物質ごとに、その危険性・有害性を特定し、労働者のばく露の可能性と程度を評価します。
リスク低減措置の検討・実施
評価結果に基づき、作業方法の改善、局所排気装置の設置、保護具の使用など、リスクを低減するための具体的な措置を検討し、実施を監督します。
リスクアセスメントの記録・見直し
実施したリスクアセスメントの結果と講じた措置を記録し、作業内容の変更や新たな情報に基づき定期的に見直します。
ばく露防止措置の実施・監督
リスクアセスメントで検討されたばく露防止措置が、実際に現場で適切に実施されているかを監督します。
保護具の選定・使用指導
適切な保護具(保護手袋、保護眼鏡、防毒マスクなど)を選定し、その正しい使用方法を労働者に指導します。
局所排気装置等の点検・維持管理
局所排気装置やプッシュプル型換気装置などが適切に機能しているか、定期的な点検とメンテナンスを監督します。
作業環境測定の実施・評価
必要に応じて作業環境測定を実施し、化学物質の濃度が許容範囲内にあるかを確認し、評価します。
労働災害発生時の対応
万が一、化学物質による労働災害が発生した場合、化学物質管理者は迅速かつ適切に対応する責任があります。
- 応急処置の指示…被災者への応急処置を指示し、医療機関への搬送手配を行います。
- 原因究明…災害の原因を詳細に調査し、再発防止策を検討します。
- 関係機関への報告…労働基準監督署などの関係機関へ速やかに報告を行います。
記録の作成・保存・周知
化学物質管理に関するさまざまな記録を作成し、適切に保存し、必要に応じて労働者に周知します。
- リスクアセスメントの実施記録
- ばく露防止措置の実施記録
- 保護具の選定・使用状況の記録
- 教育訓練の実施記録
- 作業環境測定の結果記録
これらの記録は、法令遵守の証拠となるだけでなく、将来的な改善活動や監査の際にも重要な情報となります。
義務化違反時の罰則と法的責任
化学物質管理者の選任義務を怠ったり、その職務が適切に遂行されなかったりした場合、事業者には重い罰則や法的責任が課せられる可能性があります。
中小企業の工場長や研究室長は、そのリスクを十分に理解しておく必要があります。
選任義務違反の罰則内容
労働安全衛生法第12条の5に基づき、化学物質管理者の選任義務を怠った場合、事業者には以下の罰則が適用される可能性があります。
6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金
これは、労働者の安全と健康を守るための重要な義務であり、その違反は厳しく罰せられます。
また、法人に対しても両罰規定が適用され、法人そのものに罰金が科せられることもあります。
業務不履行による責任
通化学物質管理者を選任したとしても、その者が職務を適切に遂行せず、結果として労働災害が発生した場合は、事業者にはさらに重い責任が問われる可能性があります。
安全配慮義務違反
労働契約法第5条に基づき、事業者は労働者が安全に働けるよう配慮する義務があります。この義務を怠ったと判断された場合、民事上の損害賠償責任が発生します。
業務上過失致死傷罪
労働災害により労働者が死傷した場合、事業責任者や安全管理担当者が業務上過失致死傷罪に問われる可能性もあります。
これらの責任は、企業の経営を揺るがすだけでなく、個人のキャリアにも大きな影響を与えることになります。
企業が負うリスク
義務化違反や業務不履行は、罰則や法的責任に留まらず、企業全体に多大なリスクをもたらします。
社会的信用の失墜
労働災害の発生や法令違反は、企業のブランドイメージを著しく損ない、顧客や取引先からの信頼を失う原因となります。
損害賠償請求
被災した労働者やその家族から、多額の損害賠償を請求される可能性があります。
事業活動への影響
労働基準監督署からの改善命令や、場合によっては事業停止命令が出されることもあり、生産活動や研究活動に深刻な影響を及ぼします。
優秀な人材の流出
安全管理体制が不十分な企業は、従業員から見放され、優秀な人材の確保が困難になります。
これらのリスクを回避するためにも、化学物質管理者の選任と、その職務の適切な遂行は、事業場にとって最優先事項と言えるでしょう。
まとめ
2024年4月からの化学物質管理者の義務化は、中小企業の製造業工場長や大学・大学院の研究室長にとって、避けては通れない重要な法改正です。
本記事では、義務化の背景から対象事業場、選任要件、具体的な業務内容、そして違反時の罰則と法的責任までを詳しく解説しました。
化学物質管理者の選任は、単なる法令遵守に留まらず、従業員の安全と健康を守り、企業の持続的な発展に貢献する重要な取り組みです。
適切な対応を速やかに実施し、安全で安心な職場環境を構築しましょう。
化学物質リスクアセスメントのやり方とは?頻度は?法改正や義務化についても解説!
研究施設の設計・移転はお任せください
分析・測定・制御機器の販売およびコンサルティングを事業展開している江田商会が、研究室の移転に伴う、研究機器・設備周りの配線や研究室デザイン、内装・設備工事など、移転に必要な作業をすべて請け負います。